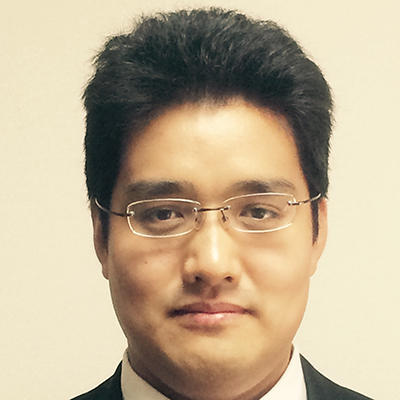12月26日(土)13時から、世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)が、高校生や教職員を対象にシンポジウム「WPIから世界トップレベルの研究者がやってくる!」(オンライン)を開催しました。
13の世界トップレベル研究拠点から研究者がやってきてお話します。研究者をめざす方や、サイエンスにご興味のある高校生はぜひご参加ください。
概 要
| 配信日時 |
12月26日(土)13:00-15:00 (オンライン開催)
|
| タイトル |
パラレルセッション3「Life Scienceのすゝめ-統・免・眠・変・微-」【理学・工学・医学・生命科学】 |
| 事前登録 |
高校生向けWPIシンポジウム2020特設ページの[参加申し込み]より行ってください。 |
パラレルセッション3「Life Scienceのすゝめ-統・免・眠・変・微-」講演者紹介 (講演順)
- 中澤 直高 iCeMS:京都大学 物質-細胞統合システム拠点
- 村上 真理 IFReC:大阪大学 免疫学フロンティア研究センター
- 坂口 昌徳 IIIS:筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構
- 中川 彩美 ITbM:名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所
- 中山 隆宏 NanoLSI:金沢大学 ナノ生命科学研究所
 |
iCeMS中澤直高先生
「メカノバイオロジー -生体における力の役割と機能-」
約100年前、Sir D'Arcy Thompsonが"On Growth and Form(邦題:"生物のかたち")"を発表しました。この中で示唆された"生体における力の役割"が分子・細胞のレベルで近年明らかとなってきており、"メカノバイオロジー"と呼ばれる研究分野として発展してきています。本発表ではメカノバイオロジーの概要、および脳のかたち作りに寄与する神経細胞のメカノバイオロジー研究を紹介します。 |
 |
IFReC村上真理先生
「腸管の免疫システムと病気」
免疫システムは体内に侵入した異物を認識し、排除する役割を持っています。しかし、本来は私たちを守るはずの免疫システムが何らかの原因により暴走し、自己の組織を攻撃してしまうことで病気を引き起こすことがあります。これが自己免疫疾患です。
一方、口から肛門までつながる消化管は体内にありながら外界とも接し、病原体や食物などの「非自己」にたえず暴露されています。そのため、腸管は免疫細胞が豊富で、緻密な免疫システムが形成されています。
私たちの研究室では腸管の免疫システムに着目し、今の医療では治すことが難しい腸管の自己免疫疾患の研究を行っています。この講演では腸管免疫の破綻と病気との関わりについてお話をしたいと思います。 |
|
 |
IIIS坂口昌徳先生
「記憶が睡眠中に定着するしくみと脳の再生能力」
大人の脳では神経細胞は再生しません。しかし脳の海馬では例外的に新しいニューロンが毎日産れます。海馬は記憶に重要です。例えば、寝ている間に海馬の神経細胞に記憶が定着します。私たちはこの過程を光を使った最新の技術で研究を進めました。そして世界で初めて睡眠中の記憶の定着には新しく生まれた神経細胞が重要であることを見つけました。将来、脳が持つ再生能力を上手く引き出し、記憶障害の治療が可能になることを夢見ています。 |
 |
ITbM中川彩美先生
「植物の気孔はどうやって作られる?〜分子を使った気孔を作るタンパク質探し〜」
皆さんの身近にある植物の表面には、空気や物質の出入り口となる気孔があります。気孔ってどんな形?どんな役割があるの?どうやって作られる?と様々な疑問が浮かぶと思います。発表では、気孔の役割や機能について解説するとともに、名古屋大学ITbMの強みを生かした気孔を作るタンパク質探しに関する最新の研究を紹介したいと思います。 |
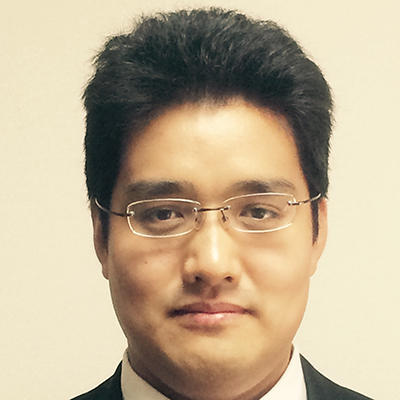 |
NanoLSI中山 隆宏先生
「ナノの生命科学って何ナノ?」
生命科学のナノの世界では、姿のある生体分子が動いて生命現象を駆動しています。Seeing is believing--その世界を理解する最も良い方法は、生体分子の姿と動きを直接見ることです。しかし、従来の方法は姿と動きを別々にしか解明できません。金沢大学が世界に先駆けて開発したナノの世界をビデオ撮影できる顕微鏡は、姿と動きを同時に観察でき、生命科学研究に変革をもたらしています。この技術を発展させて、細胞内を観察し、分子を注入・採取できるナノ内視鏡の開発を目指しています。 |
詳細は高校生向けWPIシンポジウム2020特設ページをご覧ください。